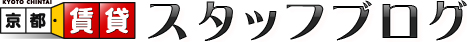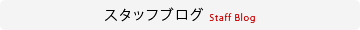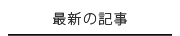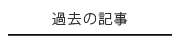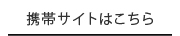| 2010年5月31日(月) 08時19分09秒 |
スタッフブログ |
世界保健機関(WHO)が発足40周年を記念して1989(平成元)年に制定しました。
1995年現在で世界の喫煙者は10億1000万人、約5人に1人の割合となっています。
職場や公共の場での受動禁煙対策や妊婦や子供対する教育などたばこ抑制策の推進について、決議や勧告を行っています。
タバコに関する昔話
むかしむかし、カナダの森のおくに、大きな木にかこまれた湖がありました。
湖の岸辺には、夫婦と二人の子どもが住んでいました。
子どもたちは大きくなるにつれて、とてもとても美しくなりました。
子どもたちが十二才になったとき、そのあたりにおそろしい病気がはやりました。
そして子どもたちは、その病気にかかって死んでしまったのです。
お母さんも悲しんで、まもなく死んでしまいました。
たった一人とりのこされたお父さんは、それはそれは悲しんで、いっそ死んでしまおうかと思いました。
でも、やっと気をとりなおして、
「そうだ、これからさき、わしは人をたすけてくらすことにしよう。人のためにつくせば、おちついたおだやかなまいにちをすごすことができるだろう」
と、自分にいいきかせたのです。
その日からお父さんは、よわいものやまずしい人たちのために、いっしょうけんめい働きました。
村の人たちは、そんなお父さんを『おじいさん』とよんで、たいせつにしてくれました。
やがておじいさんは、年をとって働けなくなりました。
みんなのために働いたおじいさんは、だれからも好かれていましたが、それでもさびしくて、たまらなくなることもありました。
たった一人でくらしていると、昼も夜もたいくつです。
ある日、おじいさんは湖のほとりにションボリすわって、おかみさんや子どもたちのことを思いだしていました。
そのとき、むこうの青くかすんだ山から、黒雲のような鳥のむれがとんできたのです。
おじいさんも、まだ見たことのない鳥です。
村の人たちは、その鳥のむれをとてもこわがって、
「あれはなにか、わるいことがおこる知らせだよ」
と、いいあいました。
まもなく、その中の一羽の鳥が羽をバタバタさせながら、地べたにおちてきました。
見ると、胸に矢がつきささっています。
村の人たちは、どうしたらよいかわかりません。
そこで、おじいさんのまわりに集まって、おじいさんの顔をジッと見つめました。
地べたにおちた鳥は、くるしそうにふるえています。
なかまの鳥たちは、しばらくそのまわりを飛んでいましたが、やがて矢のあたった一羽をのこしたまま、青くかすんだ山のほうへ帰っていきました。
「かわいそうに。けがをなおしてやろう」
おじいさんはこういって、ふるえている鳥に近づこうとしました。
すると、
「いけない! おじいさん。あれは魔法の鳥だ。きっとよくないことがおこるよ」
と、みんなはおじいさんをひきとめましたが、
「いいや、だいじょうぶ。鳥はなにもしやしないさ。それに、わしの一生も、もうおわりに近づいている。もし何かがおきたとしても、死ぬのが少し早くなるだけだよ」
おじいさんはこういって、鳥へ近づいていきました。
おじいさんが歩いていくと、あたりはきゅうにくらくなりました。
そして、鳥のすぐそばまで近づいたとき、天からまっ赤な炎のはしらがおりてきたのです。
火はあっというまに消えましたが、鳥は焼けてしまって、あとにはひとかたまりの黒い灰だけがのこっていました。
おじいさんがつえで灰をかきまわすと、中には、まっ赤な火のかたまりが一つありました。
でも、その火のかたまりもすぐに消えてしまい、あとに残ったのは、おや指ぐらいの大きさの、人のような形をしたものだけでした。
その人のような形のものが、おじいさんに話しかけました。
「こんにちは、おじいさん。あなたをたすけにまいりました」
「おまえはいったい、なにものだね?」
「わたしは、あの青い山の小人です」
そういえばと、おじいさんは、「青い山には、妖精(ようせい)が住んでいる」という話を聞いたことがあるのを思い出しました。
小人は、話しをつづけました。
「あなたに、すてきなものを持ってきたのですよ。あなたは年をとって一人ぼっちですが、あなたの一生はおわっていません。あなたはまだまだ、生きていなければいけません。あなたはおおぜいの人をたすけて、いいおこないをたくさんしてきました。これからさき、あなたがもっとたのしくくらせるように、おくりものをさしあげます」
小人はおじいさんに、小さな種をたくさんわたしました。
「いますぐこれを、ここにおまきなさい。わたしのたっている、この灰の中に」
おじいさんは、いわれたとおり種をまきました。
種はたちまち芽をだして、大きな葉をつけました。
これは、タバコの葉だったのです。
こうして鳥がもえたあとに、タバコ畑ができました。
小人は、おじいさんに大きなパイプをわたしていいました。
「この葉をかわかして、パイプにつめて、おすいなさい。きっと、たのしい気分になるでしょう。タバコは、あなたがさびしいときには、友だちになってくれるでしょう。夕方、青い光の中でタバコをすえば、煙は天にまいあがり、あなたのすてきなおくさんや、子どもたちを見まもるでしょう」
「ありがとう。ほんとうに、ありがとうよ」
おじいさんは、なんどもお礼をいって、パイプをうけとりました。
「年をとった、ほかの人たちにも教えてあげなさい。みんなたのしく、くらすことができますよ」
小人はいいおわると、遠くの青い山のほうへ、とんでいってしまいました。
それからというもの、おじいさんはまえよりも、ずっとたのしく、まいにちをすごすことができました。
タバコはこうして、カナダの森のインディアンにつたわったのです。
| 2010年5月30日(日) 08時16分12秒 |
スタッフブログ |
関東地方知事会が1982(昭和57)年から実施、各都道府県の環境美化推進協議会を中心に全国に広まっています。
「ゴ(5)ミ(3)ゼロ(0)」の語呂合わせです。
ごみやたばこのポイ捨てはやめる、ごみはごみ箱に、などマナーの実施を求めています。
| 2010年5月28日(金) 08時24分59秒 |
スタッフブログ |
1733(享保18)年のこの日、両国川開きで初めて花火が打ち上げられました。
この川開きは徳川八代将軍吉宗が行ったのが最初で、前年の大飢饉とコロリ病(コレラ)による死者の霊を慰め、悪霊を退散を祈願する水神祭として年中行事になりました。
花火に関する昔話
むかしむかし、ある森のなかに仙女(せんにょ)がすんでいました。
この仙女は、からだの半分が人間で、あとの半分がクジャクのすがたをしている魔法使いです。
森のなかまたちは、この仙女のことを「クジャク仙女」とよんでいました。
クジャク仙女は、暑い夏の日には大きな羽をマントのようにひろげて、太陽の強い光をさえぎり、寒い冬の日には、そのみごとな羽で、すっぽりと森をつつみます。
そのおかげで、森はいつも春のようです。
おまけに、クジャク仙女のからだから虹(にじ)の噴水(ふんすい)のようにふきでるふしぎな光あびて、森はいつもキラキラとかがやいていました。
どんなにおそろしいトラやライオンも、仙女がひと声さけぶと、コソコソとにげていきます。
なんともすばらしい仙女です。
小鳥も、チョウも、けものたちも、みんな仙女が大すきでしたが、とりわけ森にすむクジャクたちは、
「あの仙女さまのように美しく、りっぱになりたいものだね」
と、話しあっていました。
「でもどうすれば、クジャク仙女のような、ふしぎな力をもつことができるのだろう?」
すると、一羽のクジャクがいいました。
「そんなことかんたんさ。仙女さまから、魔法を教えてもらえばいいじゃないか」
「そうだ。そうだ。さっそく教えてもらおう」
クジャクたちはさきをあらそって、仙女のところへとんでいきました。
そして口々に、
「おねがいです。どうか、魔法を教えてください」
と、さわぎたてました。
クジャク仙女は、高い岩の上からクジャクたちを見おろしていましたが、やがて美しい声でいいました。
「今夜の三時に、ここへあつまりなさい。おまえたちのなかから、一番すぐれたものを弟子にしましょう」
クジャクたちは、ワイワイさわぎながら帰っていきました。
そして、からだや頭に花かざりをつけたり、水浴びをして、からだをきれいにしたりするのでした。
どのクジャクも、
「自分がいちばんりっぱなクジャクだ!」
と、思っているようです。
けれども一羽、自分のすがたを川の水にうつしては、ためいきをついているクジャクがいました。
「ああ、ぼくなんて、とても仙女さまのお弟子さんになれっこないや」
そのクジャクは生まれつき、からだが小さくて、羽も黒くよごれていました。
どんなにあらっても、きれいになりません。
「クジャクのくせに、きたないやつ。やーい、チビクロ!」
と、みんなからバカにされて、ろくに遊んでもらえません。
「つまらないや」
チビクロはためいきをついて、フラフラと森の外へとんでいきました。
「わあっ!」
森の外へ出たとたん、チビクロはクラクラと目がまわり、ストンと地面に落ちてしまいました。
太陽がギラギラとかがやき、燃えるようなあつさです。
そのとき、
「たすけてくれ!」
と、いう声がしました。
見ると、人間のおじいさんが、グッタリとたおれています。
あまりのあつさに、病気になってしまったのでしょう。
チビクロは、いそいでしっぽの羽をぬいて、それでせんすをつくってあげました。
チビクロがせんすであおぐと、ふしぎなことに、さあっとすずしい風がふいてきて、おじいさんはたちまち元気になりました。
「しんせつなクジャクさん。どうもありがとう」
チビクロはうれしくなって、またドンドンとんでいきました。
しばらくいくと、おばあさんがオイオイと泣いています。
「どうしたの?」
チビクロがたずねると、おばあさんはいいました。
「いま、きゅうに風がふいてきて、目に砂ぼこりがはいって、なにも見えなくなってしまったんだよ」
「それはたいへん!」
チビクロはやわらかい羽をぬいて、おばあさんの目を、そっとなでてあげました。
すると、どうでしょう。
おばあさんの目が、パッチリとひらいたではありませんか。
「あれえ!」
ビックリしたのは、チビクロのほうでした。
こんなにかんたんに、おばあさんの目がなおるとは思わなかったからです。
チビクロはうれしくて、またドンドンとんでいきました。
そのままドンドンとんでいくと、一軒の小屋がありました。
その小屋のなかから、おじいさんと男の子が出てきていいました。
「クジャクさん。はやくにげなさい! こんなところにいると、王さまの兵隊がつかまえにくるよ」
「え? 兵隊がぼくをつかまえるって? どうしてさ」
「王さまがわしに、クジャクの羽で馬車のほろをつくるように、ご命令なさったのだ」
「クジャクの羽で、ほろだって?」
「そうだ。わしは馬車づくりの職人だ。しかしクジャクから羽をむしりとってほろをつくるなんて、そんなむごいことはわしにはできん」
「それで、どうしたの?」
「それでわしは王さまに、馬車のほろをこしらえることをことわった。すると王さまはカンカンにおこって、わしをろうやに入れるというのだ」
「それじゃ、早くにげたらいいのに」
「だめだ。いまに兵隊がやってくる。わしはつかまえられてもいいが、おまえさんは森へ帰ったほうがいい。森のクジャクたちにも、兵隊がクジャクがりにくることをつたえるがいい。さあ、いそいで!」
おじいさんの話をきいたチビクロは、からだの羽をぜんぶぬいて、おじいさんにわたしました。
「こんなによごれている羽ですが、どうぞ使ってください。ぼくの羽で、馬車のほろをこしらえてください。それで、おじいさんが助かるのなら、そして、ほかのクジャクたちが助かるのなら。ではさようなら。おじいさん」
羽のなくなったチビクロは、ピョンピョンとかけだしました。
まるはだかになったけれども、チビクロはすこしもさむくありません。
チビクロのおかげで、あのおじいさんたちは、しあわせにくらすことができるでしょう。
そう思うと、心もからだもポカポカと、あたたかくなってくるのでした。
そのうちに日がくれて、夜になりました。
くらい道のむこうに、ポツンとあかりが見えます。
近づいてみると家が立っていて、中から女の子とお母さんの話し声がします。
チビクロは、そっと窓をのぞいてみました。
ランプの光の下にベットがあって、そこに病気の女の子がねています。
「おかあさま。おまつりには花火があがるでしょう。わたし、花火を見たいの。はやく、おまつりがこないかしら」
「もうすぐよ。元気になって、いっしょに花火を見に行きましょうね」
お母さんは、そっとなみだをふきました。
チビクロは、病気の女の子をなぐさめてあげたいと思いました。
けれども、チビクロにはどうすることもできません。
ションボリ森へ帰ると、ほかのクジャクたちがチビクロを見つけて、コソコソ悪口をいいました。
「あいつを見ろよ。羽が無くてまるはだかじゃないか」
「ほんと、みっともない」
「そうだ、クジャクのくせにみっともないすがたをするな! あっちに行け!」
「おまえなんか、死んでしまえ!」
チビクロははずかしくて、顔をまっ赤にして岩のかげにかくれました。
やがて、夜中の三時になりました。
さっと、ひとすじの光がさしてきて、それがあっというまに七色の光になり、くらい空にかがやきわたりました。
「あっ、仙女さまだ!」
クジャク仙女が、山の上に立っていました。
クジャクたちは、仙女の前にかけよりました。
さあ、だれが仙女の弟子にえらばれるのか、みんなはドキドキして、クジャク仙女を見あげました。
すると仙女は、岩のかげに小さくなってふるえている、はだかのクジャクをやさしくだきあげたのです。
「おまえは、人のために自分をぎせいにしました。おまえは、とてもすばらしい心を持っています。おまえこそ、わたしの弟子です」
仙女は、ニッコリ笑っていいました。
「さあ、わたしの弟子よ。病気の女の子のところへ行って、あの子をなぐさめておやりなさい」
すると、はだかのチビクロに七色のきれいな羽がはえてました。
そしてチビクロは、まっすぐ空にまいあがると病気の女の子の家にいき、美しい花火のように光かがやいたのです。
| 2010年5月26日(水) 08時47分42秒 |
スタッフブログ |
1969(昭和44)年のこの日、東名高速道路、大井松田ICと御殿場IC間が開通し、東京から愛知県小牧市まで、346キロに及ぶ全線が完成しました。
小牧ICで、先に開通した日本初の高速道路である名神自動車道と接続、東京?西宮間の536キロが高速道路で結ばれました。
| 2010年5月25日(火) 08時19分37秒 |
スタッフブログ |
1955(昭和30)年のこの日、岩波書店の国語辞典「広辞苑」の初版が発行されました。
初版の編集には7年をかけており、登録語数は20万語で定価は2000円でした。
ちなみに、当時のコーヒーは1杯50円。
字引に関する昔話
あるへっぽこ先生が、川の字と、河の字のちがいを、生徒におしえようとおもいました。
まず、川のいみをしらべようと、字引きをひきましたが、どうしてもみつかりません。
しばらく字引きをめくっていますと、三という字が、目に入りました。
それをみて先生は、ひざをたたき、
「いくらさがしても、ないはずだわ。こんなところで、昼ねしておった」
|