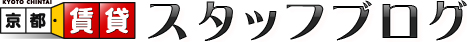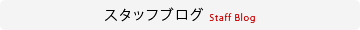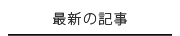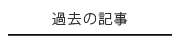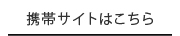| 2009年12月16日(水) 08時21分29秒 |
スタッフブログ |
東京市内と横浜市内、および両市間で電話交換業務が開始されたのが1890(明治23)年のこの日で、東京滝ノ口と横浜居留地に電話局が設置されました。
加入者数は、東京が155、横浜が42でした。
ちなみに、日本初の電話は1877(明治10)年の政府内での試験通話です。
| 2009年12月15日(火) 08時18分26秒 |
スタッフブログ |
1925(大正14)年、東京遊覧自動車会社が営業を開始したのがこの日です。
ただし、青バスと呼ばれた東京市街自動車会社が大正の半ばにすでに貸し切り自動車を使って東京遊覧を開始しており、1日コースをはじめ、2日、3日コースなどがありました。
観光に関する昔話
むかしむかし、京都に一匹のカエルがおりました。
もう、長いこと京都に住んでいたので、どこかちがう所へいってみたいと思っていました。
あるとき、大阪はとてもいい所だという話を聞きました。
「よし、ひとつ、大阪見物にでも、いってこよう」
思いたったら、もうじっとしていられません、さっそく出かけることにしました。
「よせよせ、大阪まではとても遠くて、たいへんだぞ。ケロ」
と、仲間のカエルがいいました。
「なあに、へっちゃらさ。大阪見物の話を聞かせてやるから、待っていな。ケロ」
と、いって、そのカエルは、ピョンピョンと、出かけていきました。
ま夏のことなので、お日さまはカンカンてるし、道は遠いし、カエルはくたびれてしまいました。
それでも、大阪をひと目見たいものと、ピョンピョンと歩いていきました。
さて、大阪にも一匹のカエルがおりました。
そのカエルも、もう長いこと大阪に住んでいましたので、どこかちがう所へいってみたいと思いました。
あるとき、京都はとてもいい所だという話を聞きました。
「よし、京都見物にでもいってこようか。ケロ」
さっそく、出かけることにしました。
「よせよせ、京都まではとても遠くて、たいへんだぞ。ケロ」
と、仲間のカエルがいいました。
「なあに、へっちゃらさ。京都見物の話を聞かせてやるから、待っていな。ケロ」
と、いって、そのカエルも、ピョンピョンと、出かけていきました。
お日さまは、カンカンてるし、道は遠いし、カエルはくたびれてしまいました。
それでも、京都をひと目見たいものと、カエルは、ピョンピョンと歩いていきました。
京都と大阪の間には、天王山(てんのうざん)という山があります。
「この山をこせば大阪だ。ケロ」
京都のカエルは、元気を出して、よっこら、やっこら、山を登っていきました。
「この山を越せば京都だ。ケロ」
大阪のカエルも、元気を出して、よっこら、やっこら、山を登っていきました。
お日さまは暑いし、山道は急だし、京都のカエルも大阪のカエルも、クタクタです。
二匹とも、やっと、天王山のてっペんにたどり着き、そこでバッタリ出会いました。
「あなたは、どこへいくんですか? ケロ」
「京都見物ですよ。ケロ」
「およしなさい。京都なんて、つまりませんよ。わたしは、大阪見物にいくんですよ。ケロ」
「あなたこそ、およしなさい。大阪なんて、つまりませんよ。ケロ」
そこで、京都のカエルは、立ちあがって大阪のほうを見ました。
「ほんとうだ。よく見ると、大阪も、京都とたいして変わらないや。ケロ」
大阪のカエルも、立ちあがって京都のほうを見ました。
「ほんとうだ。よく見ると、京都も、大阪とたいして変わらないや。ケロ」
それなら、いってもつまらないと、二匹のカエルは、もときた道を帰っていきました。
でも、二匹のカエルが見たのは、ほんとうは、自分たちの町だったのです。
えっ? なぜって、カエルの目玉は頭の上についているでしょう。
だから立ちあがると、後ろしか見えないんですよ。
| 2009年12月14日(月) 08時26分54秒 |
スタッフブログ |
「忠臣蔵」で有名な、大石内蔵助良雄(おおいしくらのすけよしたか)以下、四十七士が本所の吉良上野介邸に討ち入りした日です。
1702(元禄15)年12月14日の寅の上刻(午前3時)頃のことです。
赤穂浪士は一般的には四十七士とよばれるが、浪士の一人の寺坂吉右衛門は討ち入りに参加したが、泉岳寺にひきあげる途中で姿をけして切腹をまぬがれ、83歳まで生きています。
| 2009年12月12日(土) 08時19分50秒 |
スタッフブログ |
「1(いい)2(じ)1(いち)2(じ)」=「いい字1字」の語呂合わせです。
日本漢字能力検定協会が1995(平成7)年に制定しました。
この日には、全国から募集した、この年の世相を象徴する「今年の漢字」が発表されます。
漢字に関する昔話
寺子屋(てらこや→いまでいう、学習塾 (→詳細 )へはじめてかよったむすこが、先生から「一、二、三」という字を教わって帰ってまいりました。
家へ帰ると、親父さんにいいました。
「お父っつぁん、もう、先生はいらないよ」
「そいつはまた、どうしてだ」
「それじゃあいうけど、まず一という字は、こう一本ひく。二という字は、こう二本ひく。三という字は、こう三本ひく。何のことはない。かんたんなもんだ。習わなくても、あとは全部わかったよ」
「そうかそうか、えらいもんだ」
親父は、たいへんよろこんで、次の朝になると、用事をいいつけました。
「万八(まんはち)どのをよびたいから、ひとつ、手紙を書いておくれ」
「はい」
むすこは、それから部屋に入ったきり、昼になっても出てきません。
「どうしたのだろう」
と、親父は、むすこの部屋をのぞいて、
「どうじゃ、もう手紙はできたか」
と、きくと、むすこは、
「いいえ、まだまだです。ようやく、五百ばかりひきましたが、万ひくのには、明日まではかかります」
「・・・?」
親父がのぞいてみると、むすこは紙の上に一の字ばかり、いくつもいくつもひいておりました。
| 2009年12月11日(金) 08時21分39秒 |
スタッフブログ |
1975(昭和32)年のこの日、それまでの板垣退助の肖像が描かれていた百円札に替って、鳳凰デザインの百円玉が登場しました。
発効当時の百円玉は銀貨で紙幣と併用されましたが、その後、銀相場の変動により、銅75%、ニッケル25%の合金になりました。
|